『はじめてのUbuntu』が刊行されました。技術評論社刊、私は全体の監修と5章の執筆を担当しました。もっとも6-7章は特に監修することはありませんでしたが……。柴田さんが書かれたものに私ごときが手を入れるところなんてあるわけないのよわかるでしょ(威圧
元々は監修のみという話が来て、そのくらいであればと引き受けたのですが、技評社内でいろいろあって話があっちこっち行ったあと結局刊行することになり、話が進むとコマンドラインの章を書く人がいないということになり、まぁ普段から使っているしなんか書くことあるやろ、と思って気軽に引き受けてみたんですが、本当に書けなかったです。書くよりも何を書くか考えている時間のほうが長いくらいでした。あとは全ボツになった(以下自粛
ちゃやまち推しフェスティバルに行って田中真弓さんのお姿を拝見したかったな……こればかりは本当に悔やまれる……。
何を書くかも大変だったのですが、何を書かないかもなかなかに大変です。それは2段階ぐらいレベルアップしてからのことやで……とオミットしたこともたくさんあります。パーミッションに関しても紹介しない予定だったのですが、これは流石に無理でしたね。
私としては自信作と胸を張って言えるものにはならなかったのですが、柴田さんによる監修によって読めるものにはなっていると思います。表現の仕方は悪いですが(ここにはそもそもいい表現なんて何もないだろというツッコミは聞かなかったことにして)、いわゆる教科書的な内容ではなく、実際に使っている私が書いた、というのが、特徴的な何かかとは思いますが、そのあたりは読者の感想に委ねたいところです。あとはまぁスペースが空いたということでコラムを入れていて、それなりの怨念がこもっていたりするのですが、どんな怨念がこもっているのか想像してみるのも面白いかもしれません。いや何も面白くないな(怒
1~4章がGUIパート、5章がコマンドパート、6~7章が開発者向けパートと分かれています。2つに分けると5章はどっちになるのかで柴田さんと私はちょっと見解が違うようです。私は前半の方に入れて1~5章で一括りにしているのですが、柴田さんは1~4章と5~7章で括っているようです。Ubuntuを使う上でコマンドラインを使用するのを避けるのは難しいのでそうしているのですけど、でもそれってWindowsでも同じですよね。BypassNRO.cmdって何だよ。
1~5章を必要とする人は6~7章はちょっと難しいと思いますし、かといって6~7章が必要な人は1~5章は不要だと思うんですよね。ちょうどいい読者層というのがちょっと思いつかないのですけど、本まるまる1冊自分の役に立つということもレアなので、これはこれでいいんじゃないかと思います。
私としては、本書に程々に売れていただいて、技評にUbuntuの本は結構売れるんだなと思っていただいて、より突っ込んだ内容の書籍が発売されることを期待しています。別に印税欲しさで言ってるわけではありません。実際3章と6~7章はとてもいい内容だと素直に思います。
大変不幸なことに、今昨日まで本屋さんに行ってもUbuntu関連本は売ってませんでした。ムックはあるかもしれませんが。もうないかな? まぁいずれにせよ、時期的にいい感じのはずなので、どっかの学校で教科書的に使われると理想的ですよね。
あ、続刊があったとしても私は参加しません。
というわけで、最後に携わる書籍であるところの本書をよろしくお願いします!
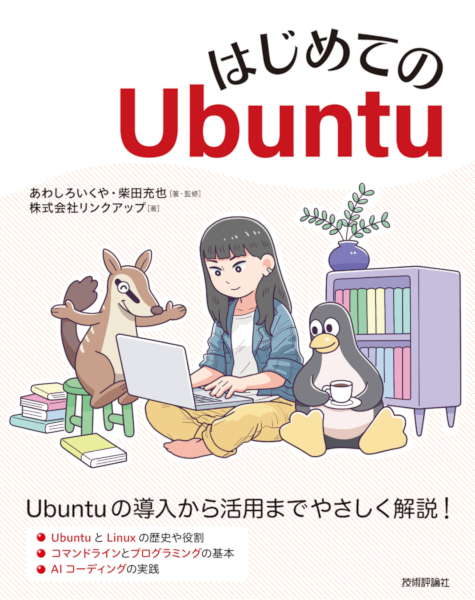
コメントを残す